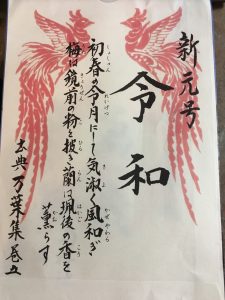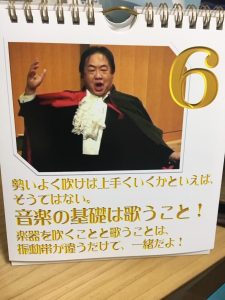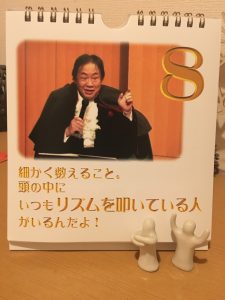2019年4月7日練習日記
久しぶりのG氏登場
練習前に「姿勢」のお話。
よい姿勢って?
気をつけ!の姿勢では楽器吹けない。
まずは身体の重心をみつけましょう。
全体の重心は床から距離が、男性が身長の65%、女性が55%
支持基底面とは
体全体を支える面のこと、ひろければ広いほど安定
両足で立ってるより、四つん這いのほうが安定
支持基底面の中心に、体の重心がくると安定する。
吹奏楽では?
立奏の場合、両足の間がこぶし 1 つくらいがちょうど安定するといわれている。後ろに重心がいってる人は、爪先立ちして親指から順に力をいれていくと、バランスがとれてくる。
前に重心がある人は、踵をつけてつま先をあげる、ちょっと痛いくらい 5 秒間 3 セット、踵側の意識がでてくる(地道な努力が必要)。
座って吹く場合
椅子に座って、ひざの後ろと椅子の間がこぶし 1 つくらい。おしりから椅子の角までが満遍なくびたっとついている状態、足裏も全部びたっとついている状態がベスト
椅子が高いと踵が上がって足に荷重がいかない、足を台にのせて直角になるように
低い場合は、クッションひいて水平に、低いと背中が曲がりやすくなる
椅子を変えるだけで呼吸がしやすくなって音がでやすくなる
ポイントは、
①身体の重心を感じる
立ってる時はおへそ下、座っている時は肋骨の下みぞおち
②ストレスを感じない位置を探す
各関節を上に積み木を乗っけていく感じ、下から順番にどこかでおさまりのよいところがあるはず。
その姿勢で楽器を持つ。楽器に口を持っていかない。
ストレスをかけない位置が見つかれば、その分肺に息がいれやすくなって吹くことにエネルギーをまわせる。
胸と背に手をあてて、前後左右に動かしたて息を吸ってみる。
どの位置が一番息が入るのかを確認してみる
貴重なお話をありがとうございます。
みんな、意識してみよう!探してみよう!身体の重心とストレスを感じない位置。
さて合奏は、2部の試奏から
皆さんのおかげで、2種類の編曲を試奏もできて、選曲には良かったですね。
続いて、1部の練習
今日の目標、「お友達を探しましょう」
(3曲目)
「何回か練習している中で、自分がメロディなのか伴奏なのか、その辺を押さえて整理がつけば良いですね。」
「頭 fpが全然きいてない!アクセントのイメージで。
2小節目 2拍目に2分音符がある人はsfzをもう少し出して。
その次のCl、Tp、Hr、Tb、Euphの付点4分音符は音価分しっかり吹いてfまで登りつめる。
タリララン、タリラランの人、食いつきが遅くなる。3連符は落ち着いて。
4小節目の山形アクセト決めて。
5小節目のB.Sax,B.Cl,Tuba,Timpの入り重要、しっかり入ってmf。裏拍から入る人は、少しテンポ感を前に。」
「A1小節前 Sax→Cl、Ob→Pic、Fl→金管、この3連符が繋がって行くように。
A2小節前 BCl、BSax、Hrの8分音符の動き、もう少し主張しても良いのでは?メロディの人もこの動きを聞いて。
A3小節前 木管は頭1拍目の裏、4拍目の裏をweight高めに。」
「B 旋律の人1拍目の意識と4拍目の3連符に重みを。4小節目のアウフタクトは繊細に入ってきて、縦を合わせて。
5小節目 Hr最後の8分音符力抜けないように」
「C アウフタクトに音をしっかり吹いて、タイの後ろの音を意識して。
メロディの人は、Bから3連符の前の8分をアウフタクトとして意識して」
「D BSax、BCl、Hr、Euph、Tb同じ音形の繰り返しは、次に向かって行く感じ。Cl、Sax、Flは、タイの音が長くて、それぞれ長さが違う、お友達の中で仲良く。
4小節目 BCl、BSax、Tb、Euphは縦を意識して、Tp、Hrは3連符の後の4分音符をもう少しはっきり。
Allegro メロディの人は、3小節目1拍目裏のテヌート短い。
意識するのは、4小節目1拍目裏と3拍目頭、5小節目1拍目裏、6小節目1拍目裏と2拍目裏。
4、5小節目の下り最後の8分音符2つが転がらないように、下りのスタッカートが待ちきれていない。
5/4は、拍頭を意識して①23、①23、①2、①2。」
「E メロディは2小節ごとパートが変わるので受渡しとダイナミクスを気をつけて。5/8の16分音符は、硬くならないように、いつもF氏が言っているようにおしゃべりするように。」
「F Andante4小節前 最後の8分音符3つの音形は次のパートへ受け継いで。
メロディがテンポ注意。
BCl、Sax、Hrは、メロディを聴きつつ、3〜6小節目の最初の2分音符までワンフレーズで。」
「G 3小節目からの16分音符の掛け合い大きすぎる。拍頭はしっかり
低音の人2分音符の和音は、輪廻転生を表現している。」
「H 金管の3小節目の各パートの入りは、アクセントをしっかり。木管の人は、金管の終わりの8分音符3つを聴いて16分音符からの4小節目頭の8分音符を合わせて決める。
Vivo 9小節目4分休符をしっかり感じて3連符ではじける感じ。」
「I Sax5小節目の16分音符はイメージを持って次の3連符に持っていく」
「J 金管は硬めに、木管はスラーなので横向きの流れで違いを出す」
「K pをぐっと落として、pの中でもどこが山なのかを表現してfへ」
最後は1部1曲目
「A、C with motionなのでテンポ感注意」
「BCl、Euph、Saxは、Dの前は3つに分けて。Eの3連符合わせて」
「I ドラムfより気持ち落とし気味にしてKとの違いを出してもらいたい。
旋律の4小節ごとの最後の4分音符は短くしないで欲しいけど、長くというより決める感じで」
以上です。
団員専用ページに「姿勢」の資料と1部1曲目の映像URLをアップします。
タップの音が頭に中で鳴るとうまく行きそう😊。
それではまた日曜日に
あと157日