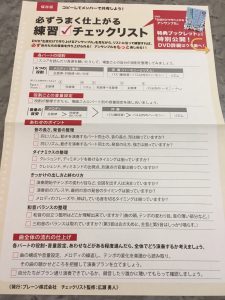2019年11月10日練習日記
朝から合奏お疲れ様でした。
クリスマスコンサートまで、あと1ヶ月となりました。
今日のF語録です!
練習の時も前にお客様が聴いている事、空間を意識して、音楽をやりましょう。
歌うこと、そのためには長い音も休符も全てカウントしましょう。
喉の後側の壁を意識して息を吹き込んで、常に頭の後ろが長くなったような感じで奥行きを意識しましょう。
それでは、また来週(^^)
寒くなりそうなので、体調に気をつけてください。
写真は、アンサンブルの譜面に付いてきたオマケですが、大事な事ばかり書いてあるので、目を通してください。